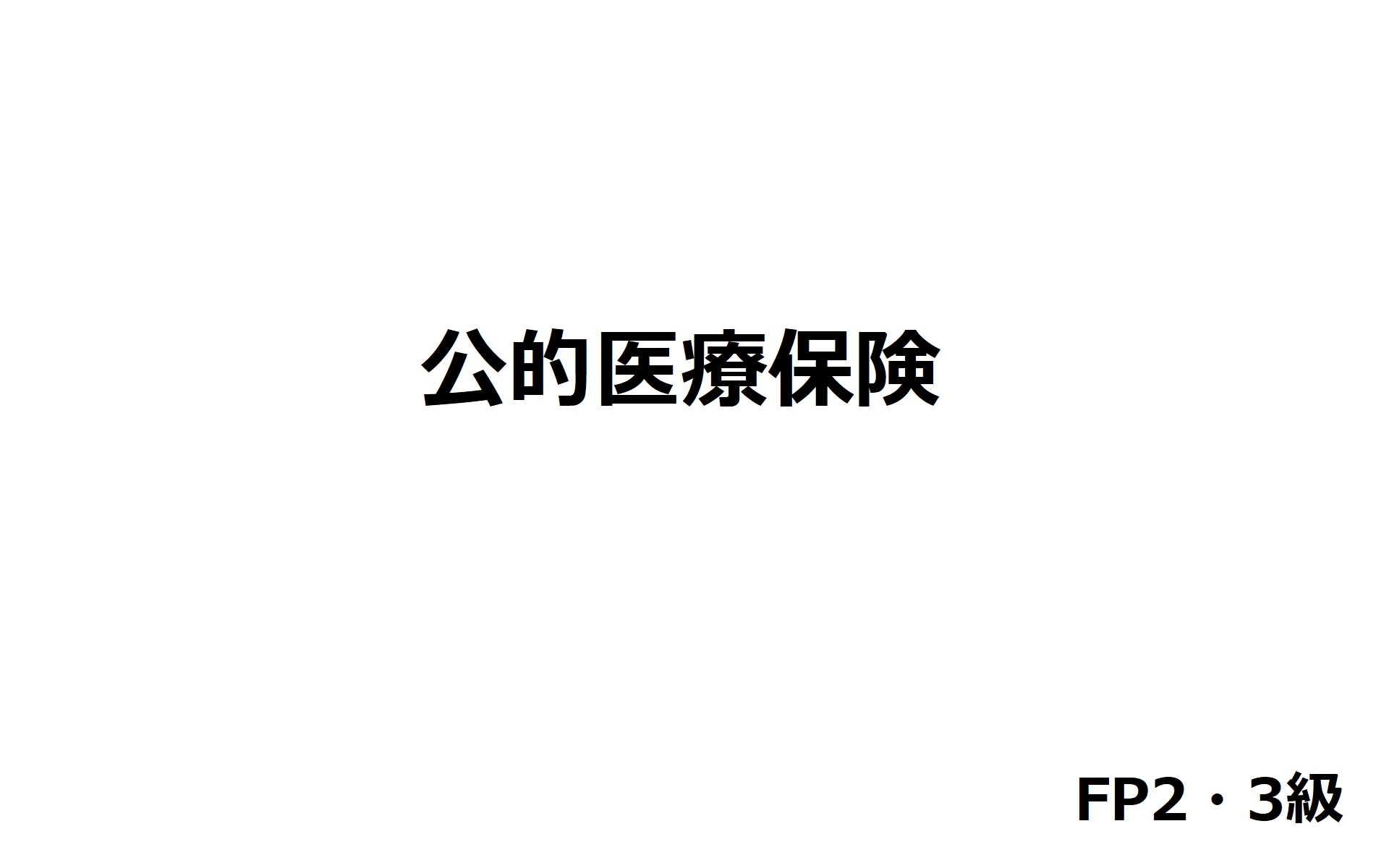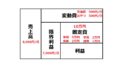保険証?病院で3割負担したら治療してもらえるすごいカードでしょ!?そんなの知ってるし!!
でも、実は公的医療保険制度には、みんながもっと安心して働いたり日常生活を送ったりできるように、いろんな面でサポートしてくれる給付があります。
今回は公的医療保険の基礎を知って、実生活・FPなどの試験の両方に役立ててくれたらと思います!

試験でも頻出だから丁寧に紹介するよ!
実際の生活、FP試験にも役立ちます!(この1記事でFP2・3級の公的医療保険の範囲を大体網羅しています)
公的医療保険
公的医療保険の全体像

日本国内に住んでいる人は、いずれかの公的医療保険に加入することが義務付けられています。

これを国民皆保険制度といい、みんなで保険料を払ってお互いを支えあう為の制度です!
公的医療保険というのは、国民健康保険、健康保険、後期高齢者医療制度の総称です。
| 保険の種類 | 加入者 | 保険者 |
| 国民健康保険 | 75歳未満の自営業者や退職者などが加入 | ・都道府県及び市区町村 ・業種別に組織された国民健康保険組合 |
| 健康保険 | 75歳未満の会社員などが加入 | ・全国健康保険協会 ・健康保険組合 |
| 後期高齢者医療制度 | 75歳以上の人が加入(年金生活者、労働者問わず) | ・後期高齢者医療広域連合 (都道府県の各区域ごとにすべての市区町村が加入) |

保険者とは保険料の徴収や保険給付を行う胴元みたいな人たちです。
以下に、各公的医療保険の仕組みや各要件、特徴などをまとめて一覧にしてみました。
被保険者や被扶養者の要件や対象などは知っていれば日常生活にも役立つと思います。
用語に慣れるために一覧の下に用語の意味も載せておきます。
各医療保険の特徴
| 国民健康保険 | 健康保険 | 後期高齢者医療制度 | |
| 加入年齢 | ~74歳 | ~74歳 | 75歳以上 (一定の障害がある場合は 65歳以上) |
| 保険者 | ・都道府県及び市区町村 ・業種別に組織された 国民健康保険組合 | ・全国健康保険協会 (中小企業) ・健康保険組合 (大企業) | 後期高齢者医療広域連合 |
| 保険の種類 | 国民健康保険 | ・全国健康保険協会管掌健康保険 (協会けんぽ):全国健康保険協会 が運営 ・組合管掌健康保険(組合健保) :健康保険組合が運営 | 後期高齢者医療制度 |
| 被保険者 | 被用者保険(健康保険等) に加入していない 自営業者、退職者等 | 健康保険の適用事業所 で働く会社員 | 75歳以上の者、または 65歳以上の一定の障害 が認められる者 |
| 保険の対象者 | 自営業者、退職者やその家族 ※未就労の配偶者、子の 保険料は世帯主が納付する | 適用事業所で働く被保険者 と被扶養者(扶養家族) ※被扶養者分の保険料負担 はない | 被保険者本人 |
| 加入要件・対象 | 日本国内に住所を有する者で 以下のいずれにも該当しない者 ・他の医療保険(健康保険) の被保険者とその被扶養者 ・生活保護を受けている者 ・後期高齢者医療制度に 加入している者 ・短期滞在在留外国人など | 従業員51人以上の企業で働き、 以下のすべての要件を満たす場合 ・週の所定労働時間が20時間以上 ・給与月額が8万8,000円以上 ・雇用期間が1年以上の見込み ・学生ではない | 75歳に到達 |
| 被扶養者の要件 | なし ※国民健康保険には被扶養者 という制度はなく、加入者全員 が被保険者となる | 配偶者、子、父母、孫、祖父母などで、 年収130万円未満(60歳以上または 一定の障害が認められる者は180万円 未満) かつ被保険者の年収の2分の1未満 | なし ※後期高齢者医療制度 には被扶養者という制度 はなく、加入者全員が 被保険者となる |
| 窓口 | ・保険者が都道府県、市区町村 ⇒市区町村役場(市役所、町村 役場、区役所など) ・保険者が国民健康保険組合 ⇒国民健康保険組合 | ・保険者が全国健康保険協会 ⇒原則、都道府県支部 ・保険者が健康保険組合 ⇒健康保険組合 | 市区町村役場 (市役所、町村役場、 区役所など) |
| 保険料負担割合 | 全額被保険者負担 | ・協会けんぽ:労使折半 (被保険者と事業主で半分ずつ) ・組合健保:事業主が必ず2分の1以上 | 全額被保険者負担 |
| 保険料算定基礎 (保険料計算の ためのベースの 賃金) | 前年の所得、家族数など | ・標準報酬月額 ・標準賞与額 | ‐ |
| 保険料(率) | ・市区町村、組合によって 異なる ・保険料には最高限度額が定め られている | ・保険者が協会けんぽ:都道府県別に 保険料率を設定 ・組合健保:組合ごとに規約で定める ・標準報酬月額および標準賞与額に 同じ保険料率を乗じて計算(総報酬制) ※事業主の申出により、産前産後休業 期間中・ 育児休業期間中の保険料は被保険者 負担分、 事業主負担分両方が免除される | ・都道府県によって異なる ・受給年金年額が18万円 以上ある場合は、原則として、 公的年金から天引き(特別徴収) ・口座振替、納付書による納付 (普通徴収)も選択できる |
| 療養の給付 家族治療費 (病院窓口での 負担割合) ※美容整形、 妊娠、出産は 対象外 | ・義務教育就学前:2割 ・70歳未満:3割 ・70歳以上75歳未満:2割 ※現役並み所得者は3割 | ・義務教育就学前:2割 ・70歳未満:3割 ・70歳以上75歳未満:2割 ※現役並み所得者は3割 | ・原則1割 ※一定以上の所得者:2割 現役並み所得者:3割 |
FP試験などを受ける人は赤字の部分は必須の知識ではあるんですが、ボク的にはまずは、日常生活と絡めて仕組みや特徴を押さえるのがおススメです。
例えばですが、この表の健康保険の「加入要件・対象」と「被扶養者の要件」などは、世の中で言われてる130万円の壁とか106万円の壁などと絡めて考えると理解しやすくなると思います。

数字の部分は法改正とかでコロコロ変わったりするけど、仕組みはあんまり変わらないので後から変わったとこだけ覚え直せばOK!けど、仕組みの理解が曖昧だと上の級に進むほどイミフになっていき沼になっていきます。
- 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ):全国健康保険協会が運営する保険、主に中小企業に勤める会社員が加入する
- 組合管掌健康保険(組合健保):健康保険組合が運営する保険、主に大企業に勤める会社員が加入する
- 後期高齢者医療広域連合:75歳以上の医療を確保するために都道府県の各区域ごとにすべての市区町村が加入して設立された地方公共団体、手続きなどは市役所や区役所でできる
- 被保険者:保険料を納付して治療の際などに給付を受ける人
- 被扶養者:扶養されている人
- 適用事業所:常時5人以上の従業員を使用している事業所、およびすべての法人、強制適用事業所と任意適用事業所がある
- 標準報酬月額:複数月の給料の平均から算出した給料の目安、保険や年金の算定の基礎に使う
- 標準賞与額:賞与(ボーナスなど)から千円未満を切り捨てた金額、保険や年金の算定の基礎に使う
- 被用者:その会社に雇用されている人
- 加入者:被保険者+被扶養者(保険料を納付する人とその保険から給付を受けられる人)
主な保険給付(国民健康保険、健康保険)
以下は、療養の給付(病院での窓口負担)以外の主な保険給付です。

国保、健康保険共通のもの、健康保険独自のものがあります!
| 給付内容 | 国民健康保険 | 健康保険 |
| 高額療養費 | ・同一月、同一の医療機関で診察を受けたとき、支払う料金には 自己負担限度額があり、限度額を超えた分は、高額療養費が支給される ※医療費全額を支払い、後から申請して限度額を超えた分の払戻しを受ける ・自己負担限度額は被保険者の所得状況などに応じて5区分に分けられる ・事前に保険者から「限度額適用認定証」の交付(70歳以上は一部の 高所得者を除き原則不要)を受けている場合は、窓口での支払いを自己 負担限度額までにできる(マイナ保険証でも可) ・入院時の食事代、差額ベッド代などは高額医療費の対象外 例)70歳未満で標準報酬月額28万円~50万円の場合の自己負担限度額 80,100円+(総医療費‐267,000円)×1% ※試験では5区分ごとの公式は与えられるのでこの式は覚える必要は ありません ※国民健康保険は前年の世帯の所得、健康保険は標準報酬月額で区分 分けされます | |
| 傷病手当金 | なし ※任意給付 | 各受給要件を満たすと休業第4日目から支給 受給要件 ・病気やケガの療養のため ・労務不能(出勤できない) ・連続した3日間の待期期間経過後 (3日連続で出勤できない) 受給日額 直近12ヵ月の標準報酬月額を平均した額の 30分の1相当の金額の3分の2相当額 支給期間 支給を始めた日から1年6ヵ月を超えない範囲 での支給、給料が支給された場合、傷病手当金 より少ない場合は、差額が傷病手当金として 支給される |
| 出産手当金 | なし ※任意給付 | 受給要件 被保険者が出産のため会社を休み、給与が受け られないとき ※被扶養者は適用外(働いている本人が出産に より仕事に行けず給料がもらえないことを手当 するための給付なため) 受給日額 直近12ヵ月の標準報酬月額を平均した額の 30分の1相当の金額の3分の2相当額 支給期間 出産日以前42日(多胎妊娠は98日)から、 出産日の翌日以降56日までの範囲 ※多胎妊娠:双子や三つ子 給料が支給された場合、出産手当金より少ない 場合は、差額が出産手当金として支給される |
| 出産育児一時金 家族出産育児一時金 | 妊娠4ヶ月以上の被保険者、被扶養者が産科医療保障制度に加入している 医療機関で出産した場合、1児につき50万円の出産育児一時金が支給される ※産科医療保障制度に未加入の医療機関での出産:48万8,000円 ※妊娠12週以上であれば流産、死産でも支給 被保険者が出産した場合は出産育児一時金が支給 被扶養者が出産した場合は家族出産育児一時金が支給 | |
| 葬祭費 埋葬料(費) 家族埋葬料 | 葬祭費 ・実際に葬儀を執り行った 者(喪主)に支給される ・支給金額は自治体により 異なる(1~7万円程度) ・75歳以上の後期高齢医者 医療制度に加入していた者 が亡くなった場合も受け取 れる (後期高齢者医療葬祭費) | 埋葬料・家族埋葬料 ・被保険者が業務外の事由により亡くなった 場合、被保険者により生計を維持されていた 埋葬を行う者に埋葬料として5万円が支給される ・被扶養者が亡くなったときは、保険者に家族 埋葬料として5万円が支給される 埋葬費 ・埋葬する家族や親族がいない場合は、実際に 埋葬した者に5万円の範囲内で支給される |
国民健康保険、健康保険はそれぞれの負担割合で治療を受けられるだけではなく、
- 医療費が自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費の支給
- 子どもを産んだ時は出産育児一時金
- 家族が亡くなった場合の葬祭費や埋葬料
など、いろんなサポートがあります。
給付について知っておくと、いざというときに大きな助けになると思います。

保険者によっては給付について知らなくて申請してなくても自動給付してくれるトコもあるけど、国保なんかは原則申請が必要なので知っといた方がいいね!
※高額療養費、出産育児一時金の申請をせずに医療費、出産費用の支払いを自腹でしちゃった!という人も2年以内なら後からの申請でも給付を受けられます。
退職後の公的医療保険への加入
会社員などが退職後に利用できる公的医療保険です。
| 健康保険の 任意継続被保険者 | 退職後、健康保険の資格喪失時に希望し、要件を満たしていれば2年間 健康保険の任意継続被保険者となることができる 要件 ・継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること ・退職日の翌日から20日以内に申請すること 退職前からの変更点など ・保険料は全額自己負担となる 保険料の算定基礎は、 「退職時の標準報酬月額」 「当該健康保険の全被保険者の標準報酬月額の平均額」 のいずれか少ない方の金額 ・原則、在職中と同様の保険給付を受けることができるが、 傷病手当金、出産手当金は支給されない ※ただし、継続して1年以上被保険者であった者は資格を 喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金は 継続して受けることができる ・被扶養者の要件を満たす配偶者や子がいる場合は被扶養者 とすることができる |
| 健康保険の被保険者 になっている家族の 被扶養者になる | 退職後、収入面などで被扶養者の要件を満たしていれば、健康保険の 被保険者である家族の被扶養者となることができる |
| 国民健康保険の 被保険者になる | 退職後、住んでいる都道府県および市区町村の市役所などで14日以内に 資格所得の届出をする |
退職後にどの公的医療保険に加入するかは、家族の人数、退職前後の収入などを考えて決める必要があります。

例えば、家族がたくさんいる場合は、国保だと世帯主が全員分の保険料を納めないといけないけど、その家族が要件を満たしてれば任意継続被保険者の被扶養者にできるから家族全体でみたら節約になる!とかね。
おわりに
これで公的医療保険の学習はおしまいです。
最初のうちはスゴく複雑な内容に感じますが「何のためにその制度があるのか」「自分や家族がどんな時にその給付を受けられるのか」を考えながら学習していけば、効率よく覚えられると思います。
病院での治療以外にもいろんな給付がある公的医療保険、しっかり覚えていざというときに恩恵を受けましょう。

では、おつかれさまでした!!