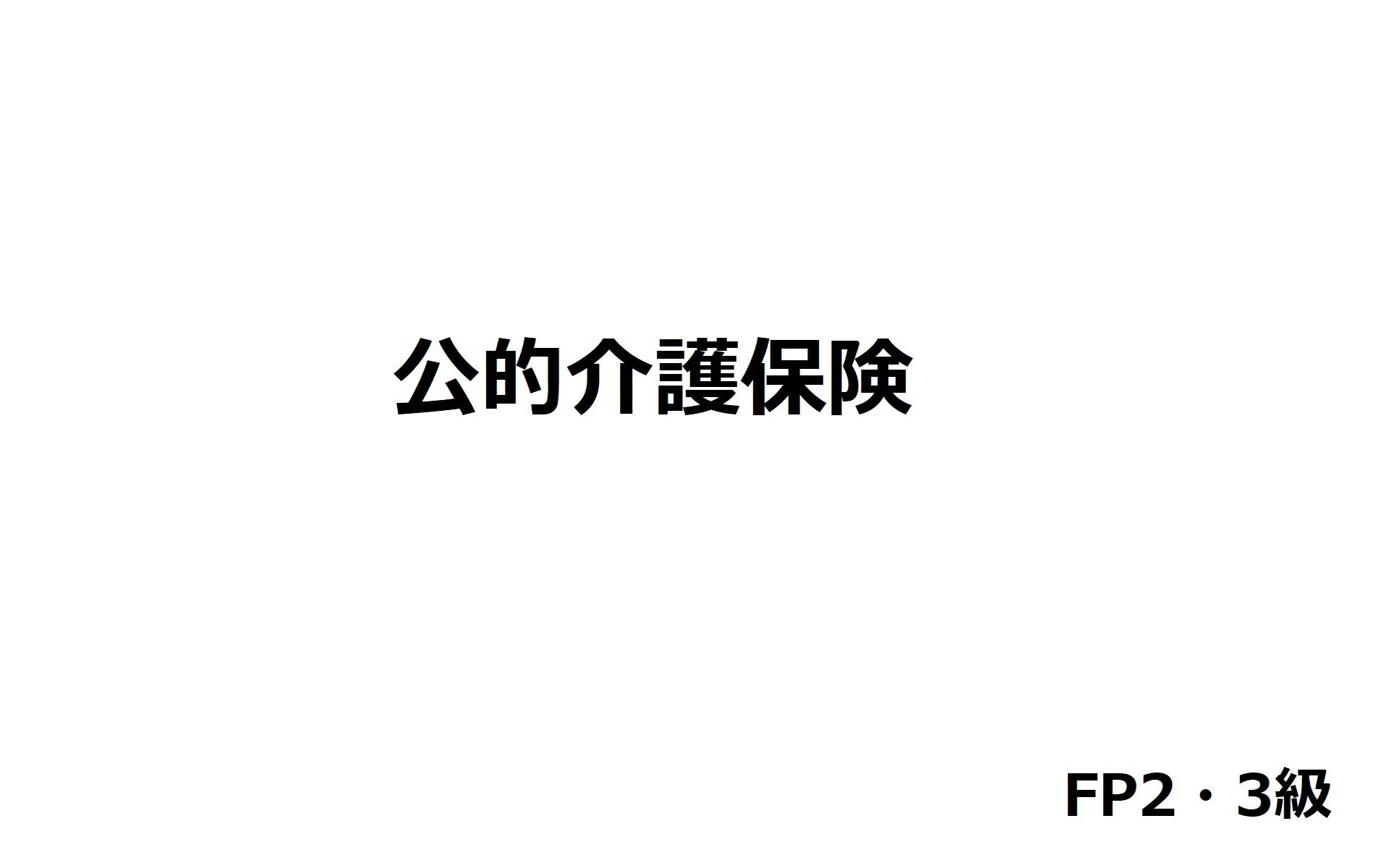前回の公的医療保険・後期高齢者医療制度に続き、今回は公的介護保険の基礎です。
介護保険?ってあまりピンとこないかもしれませんが、加齢や特定の病気により要介護・要支援の認定を受けた際に、いろんな介護サービス(原則1割負担)を利用できるという制度のことです。

学んでおくと親やじいちゃんばあちゃんが介護が必要になった時に、サクサク対処できて活躍できるかもしれません。
実際の生活、FP試験にも役立ちます!(この1記事でFP2・3級の公的介護保険の範囲を大体網羅しています)
公的医療保険の基礎はコチラ!
公的介護保険
公的介護保険の被保険者とその区分等
40歳以上の公的医療保険(国保・健康保険)の加入者は、同時に公的介護保険の加入者(被保険者)にもなります。(加入は義務であり、任意脱退はできない)
以下は、公的介護保険の被保険者の区分や詳細の一覧です。
| ‐ | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
| 保険者 | 市区町村 | |
| 被保険者 | 65歳以上の者 | 40歳以上65歳未満の 公的医療保険の加入者 |
| 受給権者 | 原因を問わず 要介護1~5と認定された者 要支援1~2と認定された者 | 特定疾病(末期のがん、関節リウマチ等) により 要介護1~5と認定された者 要支援1~2と認定された者 |
| 保険料(率) | 年額18万円以上の公的年金受給者は 公的年金から天引き(特別徴収) それ以外の場合は納付通知書、 口座振替で納付(普通徴収) | 協会けんぽは健康保険と併せて 労使折半(介護保険料率は全国一律) 国民健康保険は所得割、均等割等 (市区町村により異なる) |
| 自己負担割合 | ケアプランの作成は自己負担なし(無料) ケアマネージャーに依頼して作成するのが一般的だが、 被保険者が自分で作成することも可 利用限度額の範囲内で原則1割負担、 一定以上の所得の者は2割または3割負担、 施設サービスの居住費、食費は利用者の全額負担 | |
| 給付 | 3種類の給付 ・介護給付‐要介護者に対する給付 ・予防給付‐要支援者に対する給付 ・市町村特別給付(任意)‐要介護者、 要支援者に対する給付 | |
- 第2号被保険者は交通事故などで要介護・要支援状態になった場合は給付を受けられない(特定疾病が原因の場合のみ)
- 居宅サービス等を利用する場合は、要介護状態区分ごとに支給限度があり、サービス利用が限度額を超える場合、全額自己負担となる
- 1ヵ月の自己負担額には上限が設定されており、超えた分について高額介護サービス費が支給される
- 要介護認定を受けた被保険者が、居宅を介護に適した状態に改修を行った場合に居宅介護住宅改修費(介護予防住宅改修費)として改修費用(上限20万円)の7~9割が支給される

居宅介護住宅改修費の支給対象となる住宅改修は廊下や浴室に手すりを設置したり、段差をなくしたりなど、要介護者の介護に役立つもの、介護をする人の負担を軽減するものが対象!
介護(支援)の認定
給付を受ける(サービスを利用する)ためには、市区町村の介護認定審査会による要介護認定で要介護・要支援状態であることを認められる必要があります。
要介護認定区分は、最も介護度が軽度な要支援1~最も重度な要介護5まで区分分けされています。

要介護なのか要支援なのか、どの程度介護もしくは支援が必要なのか、で受けられる給付(利用できるサービス)が異なります。
| 要介護認定の流れ | |
| 1. | 市区町村の窓口等で要介護認定の申請をする |
| 2. | 【審査】 ・市区町村職員による訪問、聞き取り調査(認定調査) ・医師の意見書(主治医意見書)の作成 ・認定調査の結果、主治医意見書をもとにコンピュータによる1次判定 ・1次判定の結果、主治医意見書をもとに介護認定審査による2次判定 |
| 3. | 【認定】 ・要介護1~5⇒ケアプラン作成⇒介護給付 ・要支援1~2⇒ケアプラン作成⇒予防給付 ・非該当 |

判定された要介護度によって、自分が受けられる介護サービスなどについてケアプランを作成し、そのケアプランをもとにサービスの利用を開始します。
介護給付・予防給付
要介護(要支援)認定を受けた場合に受けることができる給付(利用できるサービス)についてです。
- 介護給付:要介護1~5の認定を受けた者が受けられる
- 予防給付:要支援1~2の認定を受けた者が受けられる
| ‐ | 介護給付 | 予防給付 |
| 給付の目的 | 介護・リハビリ・医療などの面 から要介護者を支援する | 要介護状態になることを予防し、 日常生活の支援、リハビリなどの サポートで自立を促す |
| 対象者 | 要介護1~5の認定を受けた者 | 要支援1~2の認定を受けた者 |
| 給付内容 | ・居宅サービス ・施設サービス ※介護老人福祉施設(特別 養護老人ホーム)への入所は 原則として要介護3以上の者 に限定される ・地域密着型サービス | ・介護予防サービス ・地域密着型介護予防サービス |

FP2・3級を受験する人は特別養護老人ホームへの入所は原則として要介護3以上の者に限定されるということを覚えておこう!
- 特定疾病:加齢にともなって要介護状態の原因となると認められる疾病、現在16種類が指定されている(末期のがん、脳血管疾患、関節リウマチなど)
- ケアマネージャー:介護、支援が必要な人が介護保険給付を受けられるようにケアプラン(サービス計画書)を作成したり利用者とサービス事業者間の調整を行ったりする介護保険の専門家
- ケアプラン:介護を必要とする人の、支援するべきサービスや目標をまとめた計画書
おわりに
今回は公的介護保険の基礎でした。
公的医療保険のときも言いましたが「誰が対象の制度なのか」「申請から認定までの流れ」「どんなサービス(給付)を受けられるのか」を整理しながら学習すると覚えやすいと思います。
公的医療保険はケガや病気に備えるための制度、公的介護保険は介護や支援が必要になったときに備える制度、という感じに各保険制度の目的や対象、給付の違いも整理しておきましょう。

では、おつかれさまでした!!